指導で疲れ果てないために、おすすめしたい態度
後輩や部下の指導に携わっていると、
知らず知らずのうちにストレスがたまり、
「もう限界…」と感じてしまうこともありますよね。
でも、そのまま我慢していると、自分も相手もつらくなる一方です。
本記事では、指導で疲れ果てないために
おすすめしたい態度や考え方をご紹介します。
できないという前提
新人や後輩は「わからないのが当たり前」。
この視点を持つことが、ストレスを軽減する第一歩です。
自分が今できていることも、
かつては先輩に教えてもらったはず。
特に教えたことのない技術や考え方については、
少なくとも自分が一度も口にしていなければ
部下は知らないモノ・コトという前提に立つと
良いと思います。
「うちの会社ではそんなん常識じゃん…」
もしかすると、その子は環境が悪く
その「常識」を誰からも学べなかったのかもしれません。
ここでその心の声を発しても
自分のイライラが少し発散されるだけで
言われた方としてはどうしようもありません。
改善点を言葉にする
たとえば、「あなたはダメだ」ではなく、
「この点に関して改善の余地がある」と伝えるように心がけます。
事実ベースで伝えることで、改善意欲を引き出せます。
「この資料、わかりにくい」
このような正直な声は
どうしても漏れてしまうことがあります。
正直な声を聞いた側からすると
自分がやってきたことを否定され、
ときにショッキングな気持ちになるものです。
そんな場合も
「ここは気づいていないかもしれないけど
二つの点を混ぜて書いていて…」
などと具体的な言葉にしてあげると
後輩も納得しやすいです。
納得感は、次は失敗しないように気をつけよう
という次回へのやる気につながります。
イライラは厳禁!
イライラしても状況は良くなりません。
むしろ、関係が悪化するリスクすらあります。
「何度言ってもわからない」
「また同じミスをしている」
そんなとき、ついイライラしてしまうのは自然なことです。
筆者も
以前同じことを言ったのに何回目だ…?
とイラりと来たことは行くたびあります。
でも、感情的になると、
相手も委縮して学びの姿勢を失い、
指導の効果がどんどん下がってしまいます。
また怒りに任せて
理性で考えていれば普段口にしない言葉
を発してしえば、
仕事上の上司と部下という信頼関係は
容易く壊れてしまいます。
イライラに気づいたら
そもそもイライラすることを
完全に防ぐことはできません。
面倒見がいいあなたは
後輩とコンタクトを取りすぎているのかもしれません。
この場合、少し後輩と距離をとったほうが
お互いのためになるケースもあるでしょう。
ただし、完全に放置すると
思いもよらぬ、間違った方向に
仕事が進んでいたりします。
半日に一回程度の声かけに頻度を少なくする
とすれば、自分の仕事も集中できるようになり
フラストレーションは溜まりにくいです。
いつ教育をするか
忙しい合間に指導しようとすると、
自分の心に余裕がなくなりがちです。
ただし、自分の仕事もあるため忙しいから
面倒を見れないと言っていては
教育が進まないのも事実。
下記では、おすすめのタイミングを紹介します。
自分の仕事がひと段落した時
最適なタイミングは、自分の仕事がひと段落したとき。
このときなら頭も心も落ち着いていて、
相手にじっくり向き合うことができます。
“今じゃない”と感じたら、後回しにしてもいいんです。
逆に忙しいときにコンタクトを取っても
早く会話を終わらせて
自分のことに集中したい雰囲気が出てしまいます。
「ひと段落したとき」
言い方を変えると、「キリがいいところで」
となるでしょうか。
逆にキリが悪くても
自分の仕事に比較的猶予があって余裕があれば、
気分転換に声をかけてみてもいいかもしれません。
(相手に嫌われていなければ、)
ときどき声をかけてくれるいい先輩のように
相手からは思われるかもしれませんね。
すぐフィードバックすべきケース
とはいえ、すべてを後回しにしていては、相手の成長の機会を逃してしまいます。
以下のような場合は、できるだけ早く伝えるのがおすすめです。
- 大きなミスにつながる恐れがあるとき
- 同じ失敗を2回と繰り返して欲しくない場合
- 誤解を生んでしまいそうな行動があったとき
筆者の場合、下記のようなケースで
幾度となく注意を繰り返してきました。
- 報連相がなかったとき
- お客さんとの打ち合わせ終了直後
教育がうまくいかない原因は誰にあるか
後輩がなかなか育たないとき、
「あの子は向いてない」
と片付けたくなることもあるかもしれません。
でも、一歩立ち止まって、
自分の教え方や関わり方を振り返ってみるのも大切です。
「伝えた」ではなく「伝わったかどうか」が大事です。
課題のレベルは適切か
課題が難しすぎて自分の力だけでは
どうにもならず途方に暮れた経験はないでしょうか。
後輩が課題に取り組めなければ
最悪、納期に間に合わず
指導者本人が率先して取り組む必要があり
自分の仕事と合わせて2倍働かないといけない。
後輩はといえば、
自分では課題に立ち向かえない無力感だけが残ります。
課題が簡単すぎると、難しすぎる場合よりは
深刻ではないかもしれませんが
時間がもったいないことは否めません。
「ちょっと背伸び」がちょうどいい
ギリギリ手が届きそうなラインの課題を用意することで、
達成感とやる気の両方を得られます。
適切な課題を見つけるために
初めて一緒に仕事をする人に対して
適切な難易度の課題を与えるのは難しいです。
場合によっては相手とも
よく話し合う必要があるかもしれません。
「将来こうなって欲しいから、今回この点にチャレンジしてほしい」
また1か月なり半年なり、
ある程度まとまった期間で仕事を共にする場合は
最初は手探りだったとしても、
一回一回で反省をして次の課題の難易度を調節したいところです。
想定より時間がかかってしまったら
どこに時間がかかってしまったのか
次回はもっと短縮できそうか、
次回の課題の難易度について
本人ともよく相談するといいでしょう。
口頭、またはチャット一辺倒になっていないか
伝え方も重要なポイントです。
口頭で説明しても忘れてしまうこともありますし、
チャットだけだと意図が伝わりにくいこともあります。
組み合わせて伝えるのがベスト
- 口頭で要点を伝える
- チャットで補足や記録を残す
- 時には図解やマニュアルも活用する
相手に合わせた伝え方を心がけるのも大事ですし
口頭の方が大事な点を素早く伝えられるし
温度感やスケジュール感まで誤解なく
伝えられる(と筆者は思っていますが)という
指導者側の思いも大切です。
逆に指導される側からでは
口頭だけだと頼りになるのは
自分の記憶とメモだけになるので
教育者から作業メモなどを渡しておくと
安心感もあるでしょう。
適材適所という言葉あり
「この子はこの業務に向いていないかも…」と感じるときもあるでしょう。
それは決してネガティブなことではありません。
人にはそれぞれ得意・不得意があります。
無理に苦手なことを押しつけるよりも、
その人が輝ける場所を見つけてあげることが、
指導者の役割でもあります。
「センス」
「センスがない」は半分以上諦めの言葉だと思います。
ある程度時間をかけて積み上げた経験に伴って
センスが磨かれることもあるでしょう。
相性や向き・不向きもありますが、
まずはある程度「経験を積ませる」ことが大切です。
仕組み
「センス」の一言で済ませるのは簡単ですが、
仕組みが整っていれば、センスがなくても
一定の水準まで仕事の質を底上げすることができます。
諦めも必要
すべての人が、すべての業務を完璧にこなせるわけではありません。
時には、相手の限界を見極め、
「この範囲まででOK」と割り切ることも必要です。
もしかすると
あまり冴えないように見える人も
別の分野では大活躍するかもしれません。
不得意な分野で膨大な時間をかけるより
分野を変えてみた方が実りがあるケースもあるでしょう。
無理をしすぎない関係性を
どちらかが無理をして続けていても、長続きしません。
諦めとは、「切り捨てる」ことではなく、
「お互いが心地よくいられる距離感を見つけること」
と捉えてみてください。
おわりに
指導は、根気と愛情が求められる仕事です。
でも、すべてを背負い込んで疲れ果ててしまっては本末転倒。
適度に力を抜きながら、心の余裕を持って接することが、何よりも大切です。
「今の自分、ちょっと頑張りすぎかも?」と思ったら、ぜひ今回の内容を思い出してください。
本記事は下記の書籍と筆者の実体験を交えてのお話でした。



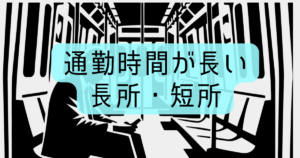
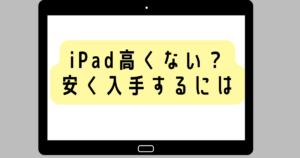


コメント